この元素サンプルは,ホウ素の単体です.ホウ素の化合物は古くから知られていましたが,単離は19世紀初頭になります.ホウ素を含む代表的な鉱物がホウ砂(borax)であり,ここからいつしかこの元素はBoronと呼ばれるようになったとされる.
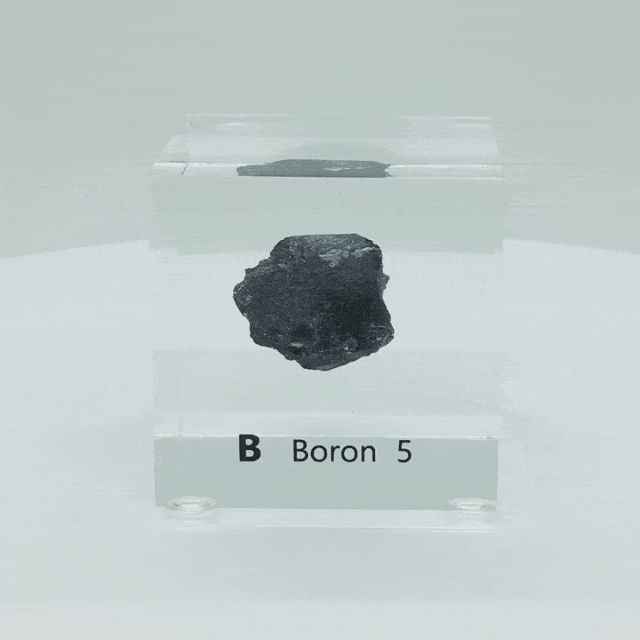
この元素サンプルは,ホウ素の単体です.ホウ素の化合物は古くから知られていましたが,単離は19世紀初頭になります.ホウ素を含む代表的な鉱物がホウ砂(borax)であり,ここからいつしかこの元素はBoronと呼ばれるようになったとされる.
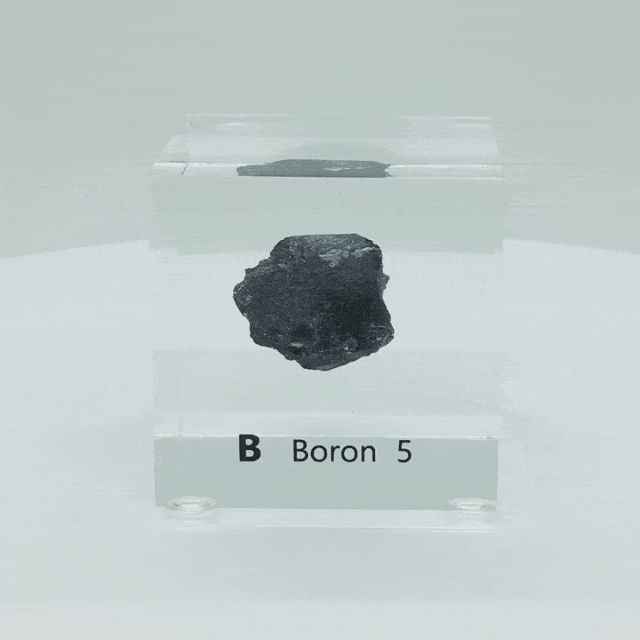
単体元素としてはあまり用途のないホウ素ですが,化合物としては結構いろいろなところで活躍している元素です.ホウ素は12原子が正二十面体型に組み合わさったクラスター構造をとりやすく,結晶中でもこの12量体が基本構造となっていることが多い物質です.単体は半導体で,バンドギャップが小さくそこそこ電気をよく流すため半金属とみなされることもあります.
ホウ素の代表的な用途の一つが,理化学用などでよく使われるホウケイ酸ガラスです.通常のガラスは,四面体状のSiO2が繋がった堅牢なネットワークをNa+やK+,Ca2+などによって崩した構造とすることで融点を下げ加工しやすくしているのですが,これら不純物のせいで熱膨張率が大きく,例えばガラス製の容器に熱湯などを入れると内側が熱で伸び,外側とのサイズのズレによって割れてしまうことがあります.ホウケイ酸ガラスは,SiO2のネットワークを切るためにホウ酸を入れたガラスです.ケイ素が4本の結合を作りやすいのに対し,価電子が1つ少ないホウ素は3本の結合を作りやすく,SiO2のSiの一部をBに置換すると結合の本数が減ります.これにより,Na+などを入れた時と同様にSiO2のネットワークを切断しながらも,熱膨張率が小さい,つまり温度差があっても割れにくいガラスとすることができます.
他の用途としては,陶器の釉薬にも使われています.ホウ素の酸化物にカルシウムなどの酸化物を加えたものは比較的低い温度で溶けガラス状となり,しかもさまざまな遷移金属イオン(※色のついているものが多い)を溶かすことができるため,これら有色のイオンを溶かし込んだ釉薬を乗せて焼くことで,きれいに色づいた陶器が作成されています.
ホウ素は哺乳類に対する毒性がかなり低い一方で,昆虫類などには強い毒性を示します.このため,昔からホウ酸団子などの形で利用されてきました.その他の用途としては,半導体であるケイ素などに微量にホウ素を加えると数桁以上も伝導性が上がることから,さまざまな半導体素子を作る際のドーパント(※一部の場所のみに導電性を出すための微量の添加剤)としても知られています.また,市販されている最強の磁石であるネオジム磁石の主な組成はNd2Fe14Bであり,ネオジム,鉄とともにホウ素が主成分として含まれています.