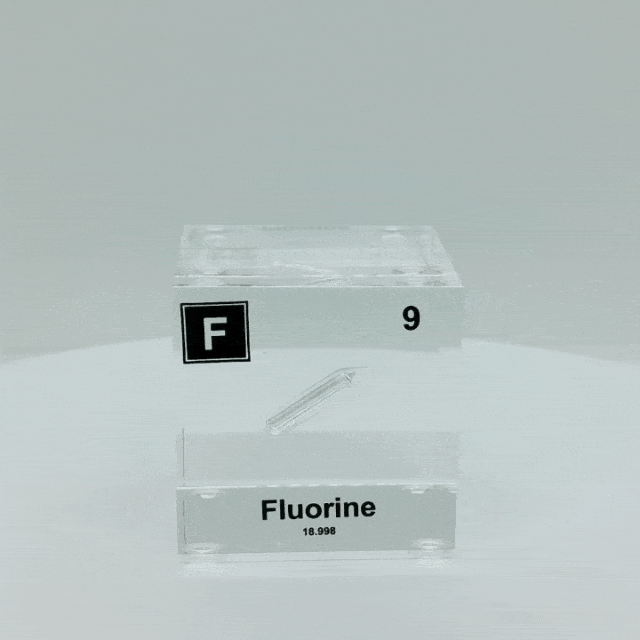この元素サンプルは,フッ素の単体であるフッ素ガス(F2)を窒素(N2)で30%以下程度に希釈し,表面をフッ素化したガラスに封入したものです.本来フッ素はガラスと反応してしまうため,ガラス中には保管できませんが,窒素などで希釈すると反応性がかなり低下し,しかもガラスの表面をフッ化ケイ素コーティングすることでさらに反応を抑えることができます(それでも,徐々に反応している可能性はありますが……).フッ素の単離は1886年にモアッサンにより達成されました.Fluorineという名のもとになったのは蛍石(Fluorite)ですが,これは製鉄の際などに蛍石を加えると不純物が液体として流れる(flow)ことに由来します.
フッ素原子Fは最も大きな電気陰性を持つ元素です.電気陰性度とは「共有結合を作った時,結合に使っている電子を自分の側に引っ張る力がどれだけ強いか?」を表す量で,これが一番大きいということはフッ素は「どの原子と結合しても,その電子を自分の側に強く引きずり込む」ということを意味しています.例えばメチル基(―CH3)の水素原子を全てフッ素に置換したトリフルオロメチル基(―CF3)では,炭素上の電子が大幅にフッ素の方に引き寄せられているため,炭素がかなりプラスに帯電した状況となります.
単体のフッ素は非常に強く電子を自分の方に引っ張り,F−になろうとする力が強い元素,つまり酸化力の高い元素です.このため単体のフッ素を単離することは困難を極めました.電気分解の方法を工夫してようやくフッ素が単離できたのは1886年で,これを成功させたモアッサンは「電極として安定度の高い白金を用いること」,「収集したフッ素の保存には,すでに十分にフッ素化されておりそれ以上フッ素とは反応のしようがない蛍石(CaF2)を用いること」,「生じたフッ素が余計な反応を引き起こすことが無いよう,低温で電解すること」などの工夫によって単離を成し遂げました.
特に化学者を苦しめたのが,フッ素がガラスと反応してしまうという点です.ガラスは非常に安定性が高く,ほとんどの化学物質と反応しないため化学では実験器具をガラスで作成しています.ところがフッ素はガラスを腐食してしまうため,フッ素の生成ではガラスを使うことができませんでした.しかし現代では,このガラスやシリコンを溶かせるという特徴から,ガラスや半導体(※おもにシリコンからできている)の加工においてフッ素は大活躍しています(しかし,時には事故が起こるため,取り扱いには十分な注意が必要です).
フッ素の用途としてよく知られているのが,テフロンです(※テフロンという名称は開発したデュポンの商標であり,物質としての名称はpolytetrafluoroethylene,PTFEが正しい).テフロンは化学における20世紀最大の発明といわれることもある物質で,長鎖の炭素鎖の周囲をフッ素原子がほとんど隙間なく覆っているため他の分子が内部に接近できず,結果として異常に安定性が高くほとんどなにとも反応しない,化学的な安定性が極めて高い物質となっています.このためテフロンでコーティングされた機器は,腐食性の高い気体や液体を取り扱ってもサビたりせず,安全に動作し続けることが可能となります.またテフロンはその棒状でほとんど曲がらない分子構造や,分子表面を覆うフッ素原子の分極率が低く他の分子との相互作用が非常に弱いことなどから,低摩擦なことも特徴です.
フッ素はまた,製鉄やアルミの精錬などでも活躍しています.これらの金属を単離する際にフッ素を含む化合物を混ぜて加熱すると各種不純物がフッ化物として溶け出すので,これを流し出すことで不純物を除きやすくできます.ほかにも,半導体素子を作る際の光源としてArFレーザーが用いられたり,薬理活性の高い分子の一部をフッ素で置換することで体内での分解を遅らせ,少量で長く効く薬剤を生み出したりと,フッ素は幅広く活躍しています.フッ素は危険な元素でもありますが,現代社会をさまざまな部分で支える働き者と言えるでしょう.
元素一覧へ