この元素サンプルは,銅の単体である金属銅がそのまま産出する鉱物である自然銅です.元素記号のCuはラテン語のCuprumに由来しますが,この語は古代ローマ時代に銅の一大産地であったキプロス島(Kypros)にちなみます.
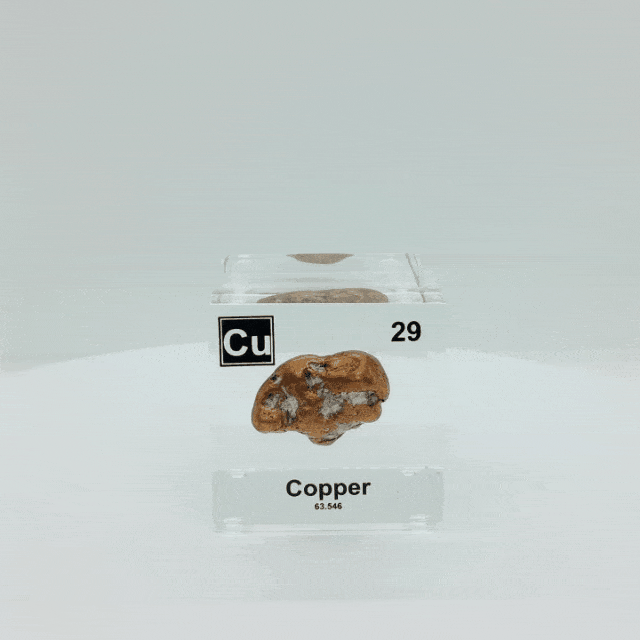
この元素サンプルは,銅の単体である金属銅がそのまま産出する鉱物である自然銅です.元素記号のCuはラテン語のCuprumに由来しますが,この語は古代ローマ時代に銅の一大産地であったキプロス島(Kypros)にちなみます.
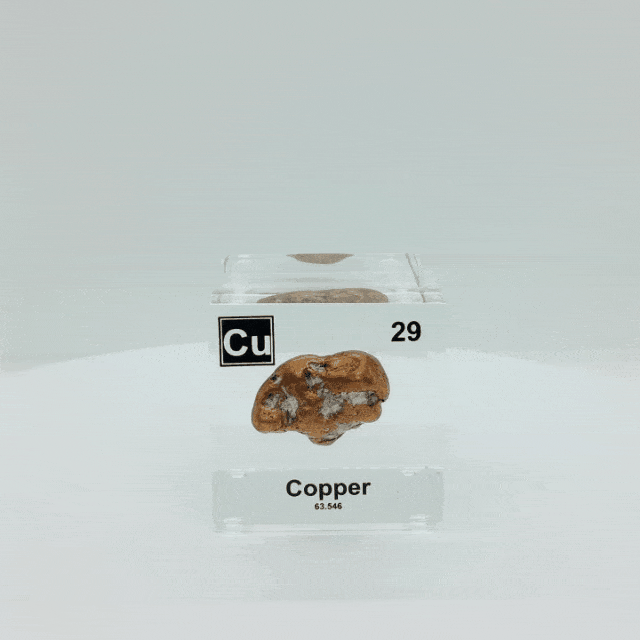
銅は鉄よりも古くから利用されていた金属です.これは銅が非常に還元されやすく,容易に金属銅とすることができたためです.周期表で銅の下に位置する銀,金も同様に中性の金属状態となりやすい金属であり,これら3種の金属は古くから貨幣として用いられてきました.このため銅などの第11族元素はCoinage metals(貨幣金属)とも呼ばれます.
銅は単体ではかなりやわらかく,熱や電気を非常によく伝える金属です.このため配線材料や調理器具としても古くから使用されてきました.銅単体ではかなりやわらかいので用途が限られますが,同じくやわらかい金属であるスズとの合金は青銅と呼ばれ,加工しやすさとともにそこそこの強度があり,古代より広く利用されてきました.例えば古代の銅剣や銅鐸などは青銅でできていますし,現代の10円硬貨なども青銅です.青銅は彫像などにもよく利用されてきましたが,水の存在下で二酸化炭素などと反応し緑青と呼ばれる青緑色の物質をその表面に生じます(鎌倉の大仏の表面などにもみられます).昭和頃まで,この緑青は毒性があると一般には誤解されており,さまざまな書籍でも毒性があるかのように記載されてきましたが,実際には緑青自体にはほとんど毒性がないことが知られています(無害というわけではないが,普通の金属イオン程度のかなり弱い毒性です).
銅イオンは,配位子が結合することで非常に鮮やかな青い錯体などを形成するため,化学において錯体を学ぶ際の見本としてもよく取り上げられます.銅イオンはまた,イカやタコ,エビやカニなどの生物における酸素輸送にも関わっています.哺乳類などは鉄イオンを含むヘモグロビンが酸素を輸送していますが,これらの生物では代わりに銅イオンを含むヘモシアニンが酸素輸送の中心をなしています.このためこれらの生物の血の色は赤ではなく,銅イオンに由来する青っぽい色をしています.一説には,これらの生物の祖先が水んでいた海底の熱水噴出孔のような環境下では一酸化炭素が存在しており,一酸化炭素と結合しにくいヘモシアニンの方が生存に有利だったのではないか,とも言われています.