このサンプルは,スズの単体である金属スズです.スズは非常に古くから知られた元素で,古代よりさまざまな金属製品や合金として利用されてきました.スズの元素記号Snはラテン語のStannumに由来します.あまりにも古くから知られている元素なので,Stannumの語源や,英語名のTinの由来などに関してはわかっていません.
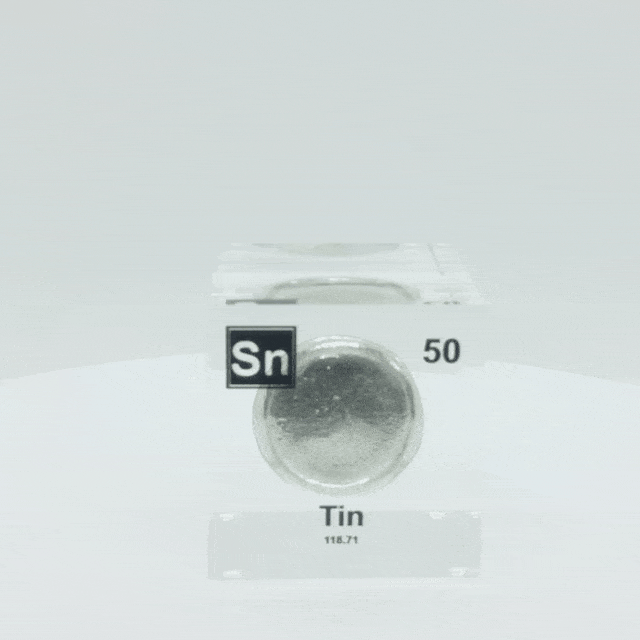
このサンプルは,スズの単体である金属スズです.スズは非常に古くから知られた元素で,古代よりさまざまな金属製品や合金として利用されてきました.スズの元素記号Snはラテン語のStannumに由来します.あまりにも古くから知られている元素なので,Stannumの語源や,英語名のTinの由来などに関してはわかっていません.
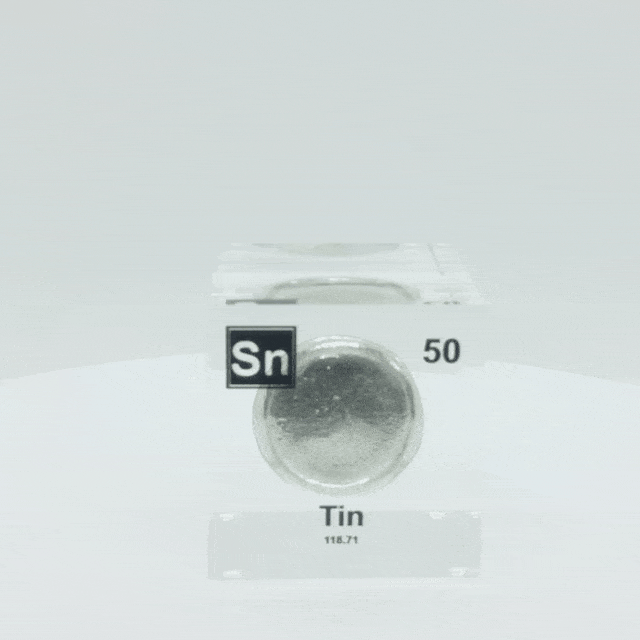
スズは非常に古くから利用されてきた金属で,紀元前3000年ごろにはすでにスズの採掘が始まっていたとされています.このころは主に銅との合金である青銅として利用されていました.スズは比較的酸化されにくく還元しやすい元素ですので,鉱石を還元しての金属の精錬も比較的容易だったようです.
現在のスズの用途としては,青銅を中心とした比較的錆びにくい合金としての利用や,低融点を活かしたハンダやウッド合金など幅広く利用されていますし,耐食性の高さを生かしたものとしては鉄の表面にスズをメッキしたブリキが良く知られています.
有機化合物とスズ原子が直接結合した有機スズ化合物がいろいろと知られており,なかでも3本のアルキル鎖が結合した化合物(トリアルキルスズ)には生物に対し強い毒性を示すものが多く,木材の防腐剤などとして利用されています.かつては船にフジツボや貝などが付着して水の抵抗を増やす(=燃料消費が激増する)のを防止するために,喫水線以下の部分にトリブチルスズなどを含む塗料を塗ることが一般的でしたが,海洋生物への影響が問題視され現在では利用が禁止されています.
近年多く使われている用途としては,インジウムとともにITO(Indium-Tin-Oxide)として透明電極となり,液晶ディスプレイや有機ELディスプレイなどの光透過性の電極としての利用が挙げられます.最近ではさらに,比較的高価なインジウムを使用しない酸化スズのみでの透明電極に関してもいろいろな開発が行われています.