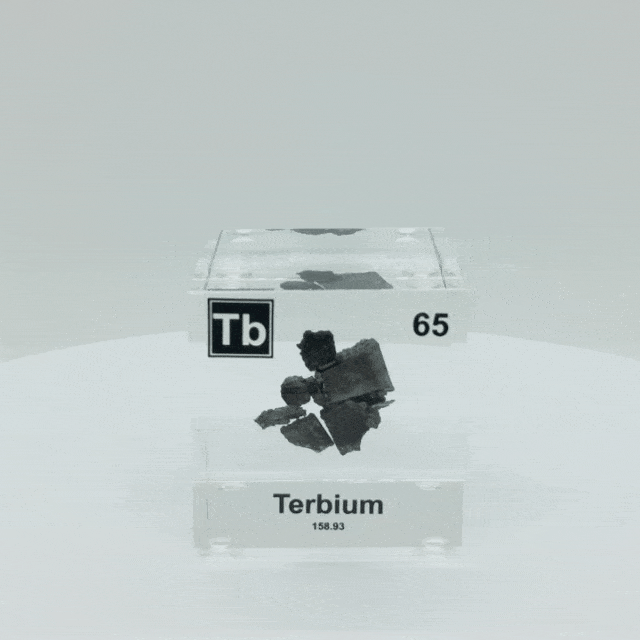このサンプルはテルビウムの単体である金属テルビウムです.テルビウムは1843年にスウェーデンのモサンデルにより発見されました.単体の金属テルビウムは1905年に得られたようです.テルビウム(Terbium)という名前は,この元素を見出したガドリン石の産地であるイッテルビー(Ytterby)にちなみます(※イッテルビーは,テルビウム以外にもエルビウム,イッテルビウム,イットリウムの名前の由来となっています).なお,もともとモサンデルは(現在で言う)酸化テルビウムを「エルビア」,(現在で言う)酸化エルビウムを「テルビア」と名付けたのですが,他の化学者が追試・検証を行う間に名前が逆に取り違えられ逆転しています.
テルビウムは銀白色の金属で,空気や水とゆっくりと反応し酸化物を生じます.テルビウムの化合物は黄色のものが多く,またそのイオンは緑色の蛍光を発することが知られています.テルビウムに限らず,ランタノイド元素は内殻のf軌道が不完全に占有された状態にあり,このf軌道の電子が絡む蛍光を示すことが多い元素です.かなり内側の軌道であるため結合や周囲の分子から隔絶されており,そのため周囲の影響をあまり受けずに決まった波長で安定した蛍光を示すことができます.このためランタノイドの錯体や微量のランタノイドを加えた酸化物は優れた蛍光材料として利用されています.
テルビウムの最も大きな利用先は,蛍光材料でしょう.テルビウムはきれいな緑色発光を示すことから,昔からブラウン管や蛍光灯の蛍光剤として使用されてきました.また,LEDなどに用いられることもあるようです.
変わったところでは,テルビウムを含む合金が非常に大きな磁歪(外部磁場に応じて伸び縮みする性質)を示し,磁場を伸び縮みといった運動に変換したり,逆に伸び縮みを磁力に変換することができます.これを利用し,潜水艦のソナーなどのセンサーや,インクジェットプリンターのヘッドなどの精密なアクチュエーターに利用されることがあるそうです.また今ではほぼ見なくなりましたが,過去の日本で多く使われた光磁気記録媒体であるMOにもテルビウムを含む合金が活用されていました.
磁気との関係で言うと,光通信の普及により利用が増している光アイソレーターにもテルビウムは利用されています.光ファイバーなどを通る光は,接合面など境界で一部が反射され戻ってきてしまいます.こういった「余計な光」が混ざりこむとノイズとなり通信が阻害されてしまいますので,「正しい方向に進む光は通すが,逆向きに戻ってくる光は遮断する(別方向に曲げる)」という素子(※電気回路で言うと,一方にのみ電流を流せるダイオードのようなもの)が重要となります.これが光アイソレーターで,ファラデー効果と呼ばれる磁場と光との相関などを利用しているのですが,テルビウムを含むガラスが利用されています.
元素一覧へ