このサンプルはジスプロシウムの単体である金属ジスプロシウムです.ジスプロシウムは酸化ホルミウム中の微量不純物として1886年にフランスのボアボードランが発見しました.純粋なジスプロシウムを得ることは難しく,単離はイオン交換法による精製が開発された1950年代を待つ必要がありました.ジスプロシウム(Dysprosium)という名は,その精製が非常に困難であることからギリシャ語の「得難い・近寄りづらい」を意味するDysprositosから命名されました.
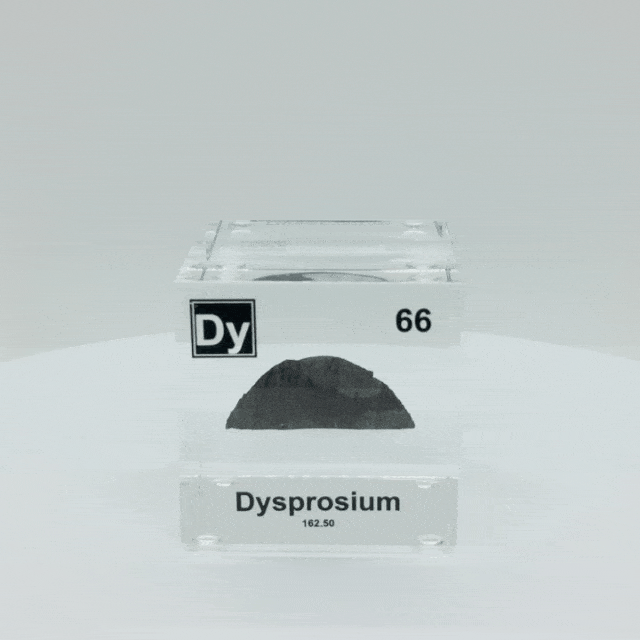
このサンプルはジスプロシウムの単体である金属ジスプロシウムです.ジスプロシウムは酸化ホルミウム中の微量不純物として1886年にフランスのボアボードランが発見しました.純粋なジスプロシウムを得ることは難しく,単離はイオン交換法による精製が開発された1950年代を待つ必要がありました.ジスプロシウム(Dysprosium)という名は,その精製が非常に困難であることからギリシャ語の「得難い・近寄りづらい」を意味するDysprositosから命名されました.
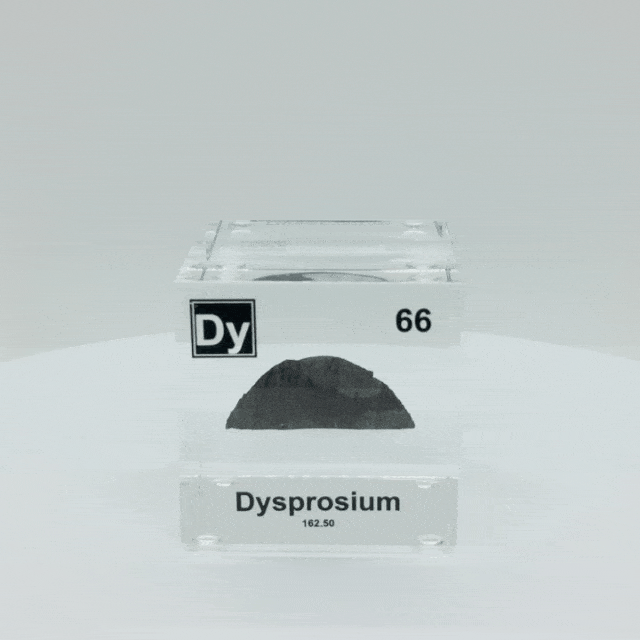
純粋なジスプロシウムは銀白色の柔らかい金属ですが,他のランタノイド元素と同じく酸化されやすく,空気や水との接触で徐々に黄味を帯びたり黒く変色してしまいます.
ジスプロシウムは磁性材料として重要で,ネオジム磁石に数%ほど加えることで異方性が大きく向上します.ネオジム磁石は非常に強力ながら熱に弱く,少し温度が上がっただけでも磁化の向きが崩れやすく,磁力が弱くなりがちです.そこにジスプロシウムを加えると異方性が増すためにスピンの向きが変わりにくくなり,多少温度が上がっても磁力を維持することが可能になります.このため温度が上がりやすいモーターなどに使われるネオジム磁石にはジスプロシウムが不可欠で,電気自動車や風力発電のタービンに使用されています.
磁力繋がりで言うと,テルビウムおよび鉄との合金であるTerfenol-Dが,非常に大きな磁歪(外部磁場により形状が少し変化する効果)を示すことが知られており,超磁歪合金などと呼ばれています.大きな磁歪を示す材料は,磁場の変化と材料の変形とを相互に結びつけますので,加わる力を磁場の変化に変換し読み取ったり,電流などにより生み出した磁場の変化を音波や運動に変換したりすることが可能で,各種のセンサー,ソナーや超音波の発生,燃料やインクの精密な噴射,工作機器のヘッド部の精密・正確な移動などに幅広く利用されています.
ジスプロシウムはまた,波長3 μm付近というやや長めの波長の赤外線(中赤外)を放射することが可能で,この波長域のレーザーや光増幅に使えると期待されています.分子はその構造に応じて中赤外領域の特定の波長に強い吸収を示すことから,中赤外での吸収を調べることでどんな分子が含まれているのかを調べることが可能です.そのため中赤外域の光源となるレーザーやLEDなどの開発が数多く行われていますが,ジスプロシウムはそんな光源の候補の一つです.
変わったところでは,ジスプロシウムが熱中性子(速度の遅い中性子)を良く吸収できるという特徴から,原子炉の制御棒などにも利用されているそうです.