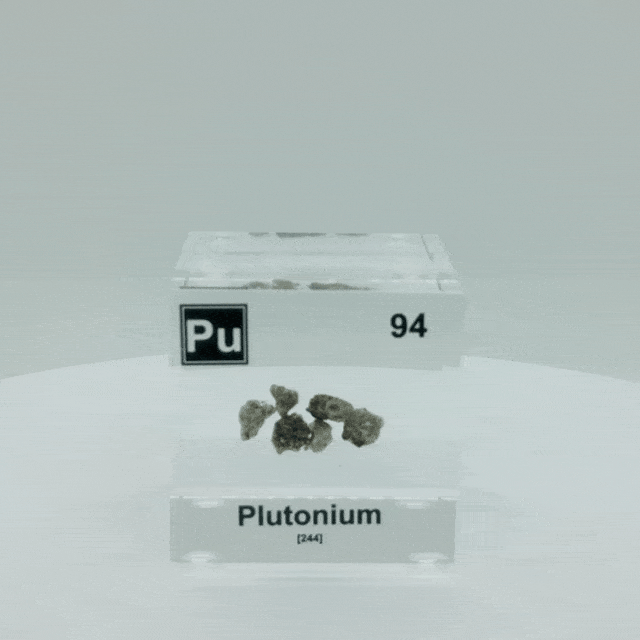このサンプルは,プルトニウムによる世界初の各実験が生み出した,微量のプルトニウムを含む(可能性のある)岩石であるトリニタイトです.プルトニウムがごく微量にウラン鉱石中に存在することを,UCバークレーのシーボルグらのグループが1940年頃に見出していました(ただし,機密事項として1946年まで公開は止められることとなります).その翌年の1941年にはシーボルグ,マクミラン,ケネディーおよびワールらはUCバークレーのサイクロトロンを用いてウランに重水素を衝突させ核融合を起こす方法で238Puの合成・分離に成功します.プルトニウム(Plutonium)という名は,冥王星(Pluto)にちなみ命名されました.
プルトニウムは天然にはごく微量しか存在せず,現在核燃料や核兵器で用いられているプルトニウムはその全量が原子炉を用いて製造されています.原子炉中で235Uが核分裂を起こす際には中性子を放出しますが,これが238Uに吸収されると2段階のβ崩壊を経て239Puとなります.現在までにはかなりの量のプルトニウムが製造されており,その特性に関してもだいぶわかっています.単体のプルトニウムは銀白色の金属であり,かなり反応性の高い元素です.
プルトニウムの用途で最大のものは,核燃料および核兵器です.アメリカがマンハッタン計画で開発した核兵器はウランを用いたガンバレル型のものとプルトニウムを用いた爆縮レンズ型の2種類がありました.ガンバレル型は構造が単純で製造しやすいものの,一度起爆シーケンスに入ると止める手段がない,ウラニウムが多量に必要である,などの欠点があり,広島に投下されたリトルボーイ以降は用いられていません.一方,周囲に適切に配置した爆薬による爆縮でプルトニウムを微小領域に圧縮し連鎖反応を起こす爆縮レンズ型の核兵器は,設計と製造が困難な一方,一度製造法が確立すれば使用する核物質の量も少なくて済み取り扱いが容易であるなど,以降の核兵器のスタンダードとなっています.しかし開発当初は爆縮がうまくいくかの確信が持てず,そのためロスアラモスにて世界初の核実験(トリニティ実験)が執り行われることとなりました.
トリニティ実験で起爆された世界初の核爆弾「ガジェット」は瞬時にTNT爆薬20キロトンに相当するエネルギーを放出,その熱輻射は爆心地の土壌を蒸発させ,核反応生成物などと混然一体となった成分は溶けたガラス状の物体となって降り注ぐこととなります.これが現在「トリニタイト」として知られる人工鉱物です.
プルトニウムは,原子力電池のエネルギー源として利用されることもあります.深宇宙探査機などは太陽からの光がほとんど届かない場所で活動する必要があり,長期間電力を出力できる電池が必要となります.このような用途向けに,プルトニウムの崩壊から出る熱や電子線を用いた動力である原子力電池が開発され,例えば太陽系を飛び出していったボイジャーや,冥王星探査機であるニューホライズン,火星での長期探査を行うキュリオシティなどに原子力電池が搭載されています.またかつては,一度埋め込めば長期間電池交換無しで動く動力ということでペースメーカーに利用されるなど,民生利用の例もあったようです.
元素一覧へ