|
磁性としては,内殻による反磁性,Pauli常磁性,局在常磁性・強磁性・反強磁性,バンド強磁性
が圧倒的に多く,これだけでほとんどの物質の磁性が説明できます.
例えば身の回りにあるほとんどのものはいわゆる非磁性体で内殻の反磁性しか示しませんし,
金属はPauli常磁性とバンド強磁性,酸化物系などで局在の強磁性・反強磁性などです.
しかしながらやはり世の中には変わったやつもいるわけでして,そういったマイナーな
存在ほど研究する上では面白いものです.ここではそれらちょっと変わった磁性体を
いくつか紹介したいと思います.
 第一近接,第二近接相互作用とも反強磁性の場合のらせん磁性(上)と,第一近接が強磁性,第二近接が反強磁性の場合のらせん磁性(下)
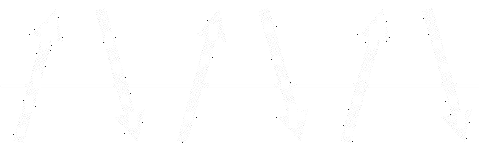 反強磁性体のスピンが微妙に同じ方向に傾くことにより全体では弱い自発磁化が 右向きに発生する.
このようなスピンの傾きの起源として主に存在するのは
まずDMですが,これはスピン-軌道相互作用に由来します.
ハミルトニアン中においてスピン-スピンの相互作用は等方的なのですが,スピン-軌道
相互作用は軌道角運動量の方向性を反映して異方的になります.
このため,「スピン-軌道相互作用によって生じる項」と「もう一つのスピン」との相互作用(1次×1次で2次の摂動になります)にも
方向が効いてきますから,反強磁性であっても単純に逆方向を向けばいい,というわけには
いかなくなるのです.
細かい式は磁性の教科書に載っているのでそれを見ていただくとして,結局項としては
d ・[Si×Sj]
という形で書き表されます.ここでd はiにおけるスピン-軌道相互作用と
jにおけるスピン-軌道相互作用(共に1次の摂動)の大きさの二項で書き表され,スピンの
交換に対して反対称です.
この相互作用はスピンのベクトル積を含みますから,エネルギーを小さくするためには
互いのスピンが90oになるように働きます.これがスピンを傾けるのです.
傾ける方向が揃えば弱強磁性になりますが,順番に違う方向を向いていくとらせん磁性になったり,
らせんと弱強磁性の混じったような磁性になったりと,実際に現れるものはいろいろです.
このDM相互作用は二つのスピンが中心対称で結び付けられるとき(両者の中点で反転
させたとき,両スピンのサイトが結晶学的に入れ替わる場合)には厳密にゼロとなります.
これはスピンの入れ替えに対してDM相互作用全体は反対称なのにもかかわらず,
同時に反転対称の存在がスピンの入れ替えに対して対称である事を要求するためです.
この両者を同時に満たすためにはDM相互作用が厳密に0でなくてはなりません.
L. Néel et al. , Pauthenet Comp. Rend., 234 (1952) 2172
追記  ということは弱強磁性にするにはスピン軸のずれていく向きを互い違いにする何かが必要なわけです. そのような原因としては,例えばスピンの異方性や,第二隣接スピン間での強磁性的相互作用 があげられます. スピンに1軸異方性が存在する場合,例えば上図の右端のスピンは軸から大きくずれているため エネルギーが高くなってしまいます. これに対し,弱強磁性を示したもう一つ上の図では各スピンの容易軸からのずれは小さく, 異方性によるエネルギーは小さくてすみます.このため,1軸異方性は弱強磁性を優先 させようと働きます. 一方,第二隣接スピン間にも相互作用が働く場合,その相互作用が強磁性なのか反強磁性なのか が大きく影響します. 上図で分かるとおり,らせん磁性的な配置を取った場合,あるスピンと第二隣接スピンとの なす角は2θとなります.一方の弱強磁性配置の場合,その角は0です. そのため,第二隣接スピン間に働く相互作用が強磁性的ならば弱強磁性配置が,逆に第二隣接スピン間の 相互作用が反強磁性的ならばらせん磁性を好むということになるでしょう. 続いて錯体などの異方性に基づくものですが,これはもっと簡単です. 例えば結晶中で錯体が交互にある方向に傾いて,かつ異方性も非常に強い場合,スピンの向きも 錯体の向きに引きずられてcollinearな構造からずれてきます.この場合もDM相互作用と同様に non-collinearな構造が基底となりますから,弱強磁性が発現する可能性は十分にあるわけです. F. Setifi et al., Inorg. Chem., 41(2002), 3786 そして最後のフラストレートがある系,ですが,これは幾何的に全ての相互作用のパスを 最安定には配置できないような場合におきます. この場合,やむを得ずちょっと傾いた方向を向くわけですが,全体の構造やら何やらが うまく組み合うと弱強磁性が生じることもあります.J. Nishijo et al., Bull. Chem. Soc. Jpn., 77(2004) 715 |